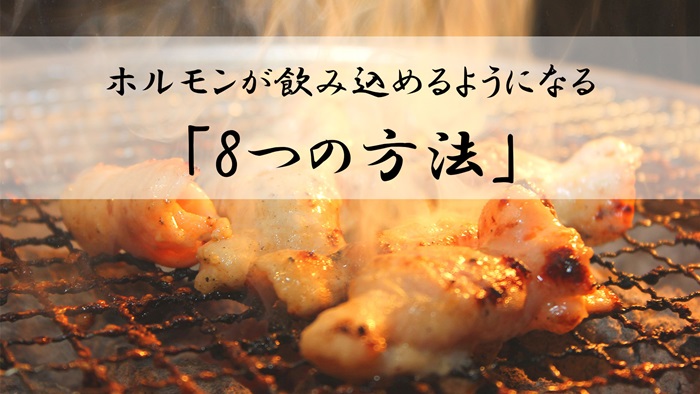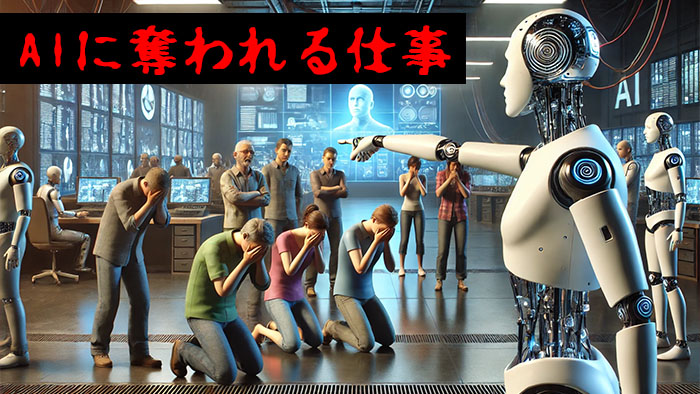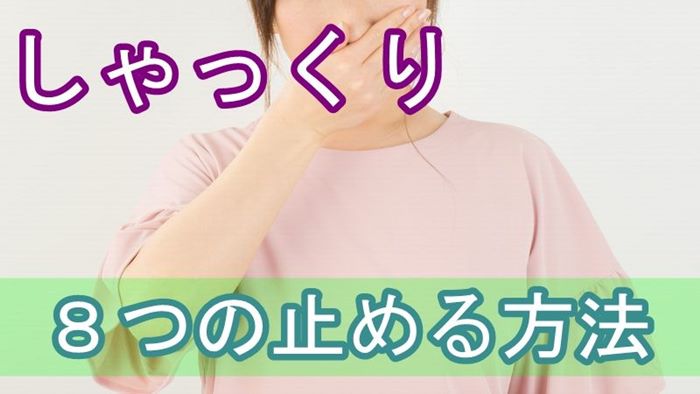
しゃっくりの原因は?止める方法は?
そもそもしゃっくりのメカニズムについて具体的に把握していない人が多いかもしれません。
「横隔膜の痙攣でしょ?」っと言われたらその通りですが、しゃっくりが起こる原因や、正しい止め方はご存知でしょうか?
今回は、しゃっくりの原因と止める方法、この両方を具体的に見ていきたいと思います。
その原因は食べ物・飲み物にもあります!
目次
しゃっくりには3種類ある!
しゃっくりは「横隔膜の痙攣」が原因ということは有名ですよね。
ではそのしゃっくりにはどんな種類があるのか見ていきましょう!
一般的なしゃっくり(横隔膜刺激)
みなさんがいつもよくしているしゃっくりです。これはお腹と胸に挟まれている「横隔膜」という部分が痙攣することで起こります。
また胃潰瘍、逆流性食道炎、食道がん、胃がんを発病されている方にも、しゃっくりを引き起こします。
一般的にほっておけば勝手に止まるもの。
危険なしゃっくり(中枢神経)
人間の神経系が集中している「中枢神経」の刺激により引き起こります。
脳の病気だったり、アルコール中毒の症状があり、一般的なしゃっくりに比べ、しゃっくりの感覚が短く、止まりにくいのが特徴。
また頭痛や吐き気といった症状も同時に引き起こることがあります。
危惧される病気はクモ膜下出血や脳梗塞、脳出血などがある。
危険なしゃっくり(末梢性)
これは中枢神経の延長にある「末梢神経」が刺激されて引き起こるものです。
脳や消化器官の病気が原因で、「肺炎」「気管支喘息」「胸膜炎」など。
中枢性しゃっくりと末梢性しゃっくりは危険性が高いので「もしかして…」っと思ったらすぐに病院へ行ってください。
しゃっくりの原因(食事編)

まずは食後にしゃっくりが出る原因を見ていきましょう。
以下の原因がしゃっくりを引き起こす原因になっている可能性が高い。
①早く食べてしまう
食事を噛まずに飲み込んでしまう人も出やすい傾向にあります。
②食べ過ぎる
胃が膨らむことで、横隔膜が圧迫され、しゃっくりが起きる。
③刺激物(七味など)を摂取する
喉の奥にしゃっくりを引き起こすスイッチがあり、そこに刺激物(辛いもの)が触れるとしゃっくりが起きる。
④炭酸系の飲み物が多い
刺激物と同様に喉の奥にしゃっくりを引き起こすスイッチがあります。そこに炭酸が触れるとしゃっくりを引き起こす場合がある。
⑤急に冷たいものを食べる飲む
冷たいもの、または温かいものを食べる、もしくは飲んだ場合、急激な温度変化でしゃっくりが起きる。
※アイスクリームやかき氷、冷たい水は注意
⑥お酒を飲み過ぎる
冷たいもの同様、急激な温度変化でしゃっくりが起きる。
※ビールなど冷たいものは注意
⑦しゃべりながら食事をする
話ながら物を食べたり飲んだりすると、食べ物、飲み物と共に空気も体内に入り、それがしゃっくりの原因になります。
食後しゃっくりを予防するには?
日常のしゃっくりの原因は不明ですが、事前に防げるものもあります。たとえば食べるスピードを遅くしたり、冷たいものや温かいものを急激に食べ飲みしないことを心掛けましょう。
もし、食後にしゃっくりが出続ける場合は「横隔膜下腫瘍」「脳梗塞」「肝臓がん」「アルコール中毒」「肺炎」「痛風」などの病気がある可能性があるので注意してください。
しゃっくりの原因(食事以外編)
では次に食事以外でしゃっくりがでる場合を見ていきましょう。
思わぬしゃっくりの引き金とは…?
①笑う
笑い方によっては横隔膜を刺激する笑い方があるそうです。(人によってその度合いは変わる)
また大声を出したときも同様です。これはもう防ぎようがありませんね…予防するより、止め方を見つけたほうがいいかもしれません(後にあらゆるしゃっくりの止め方を説明します)
②ストレス
ストレスが原因で起こるしゃっくりです。心因性しゃっくりと呼ばれており、ストレスの不安からくるもので、男性よりも女性に多く見られるそうです。
やっかいなところは通常のしゃっくりを治す方法が効きにくいというところ。ストレスの根本的な原因を治さないと、意味がないそうです。
③驚く
神経が刺激されることにより、しゃっくりが起こる。たとえば運転していて、事故になりそうになったとき、ヒヤっとしますよね?他にもお皿を落としそうになったときもそうです。
神経が刺激されその驚きで横隔膜が痙攣する場合があります。しゃっくりは驚かされると治るとよく言いますがその逆パターン。
④暖かい環境から急激に寒い環境になった場合(その逆も)
例えば冬場など暖かい暖房の効いた部屋から外へ出たとき、冷たい空気が肺に入り込みしゃっくりを起こす場合があります。またその逆もあります。
しゃっくりを止める方法

あらゆる原因で引き起こるしゃっくりですが、さてそれを止めるには?
飲み物でしゃっくりを止める
①コップの上にお箸(割り箸でも可能)をバッテン(×)にして最後まで飲みほす
②砂糖水を飲む
③レモン水を飲む
④ほうじ茶に生姜をすりおろし飲む
呼吸でしゃっくりを止める
⑤腹式呼吸で息を吸って1分息を止める。※腹式呼吸ができなければ仰向けになり、息を吸うと勝手に腹式呼吸になります。
⑥リラックスした状態で、ゆっくり10回ほど深呼吸する。
⑦紙袋で呼吸する※過呼吸になった場合の対処法と同じ
最終手段
⑧両耳の穴に指を入れて30秒待つ
上記の飲み物と呼吸組み合わせると効果絶大!
また、最後の「8」はテレビ番組でも放送された方法です。信憑性は高いと思うのでぜひお試しください!
まとめ
いつ、どこで、どんなタイミングで引き起こるかわからないしゃっくり。
予防はできますが、注意していても引き起こしてしまう時は必ずあります。そんなときはご紹介した止め方をお試しください。
それでも止まらない場合は危険性の高い病気かもしれません。すぐに病院へ行ってくださいね!
●しゃっくりの種類
・横隔膜刺激
・中枢神経
・末梢性
●しゃっくりの原因(食事編)
・早く食べてしまう
・食べ過ぎる
・刺激物(七味など)を摂取する
・炭酸系の飲み物が多い
・冷たいものを食べる飲む。
・お酒を飲み過ぎる
●しゃっくりの原因(食事以外編)
・笑う
・ストレス
・驚く
●しゃっくりを止める方法
・コップの上にお箸(割り箸でも可能)をバッテン(×)にして最後まで飲みほす
・砂糖水を飲む
・レモン水を飲む
・ほうじ茶に生姜をすりおろし飲む
・腹式呼吸で息を吸って1分息を止める。
※腹式呼吸ができなければ仰向けになり、息を吸うと勝手に腹式呼吸になります。
・リラックスした状態で、ゆっくり10回ほど深呼吸する。
・紙袋で呼吸する※過呼吸になった場合の対処法と同じ
・両耳の穴に指を入れて30秒待つ